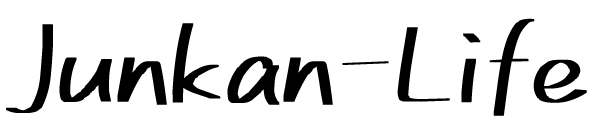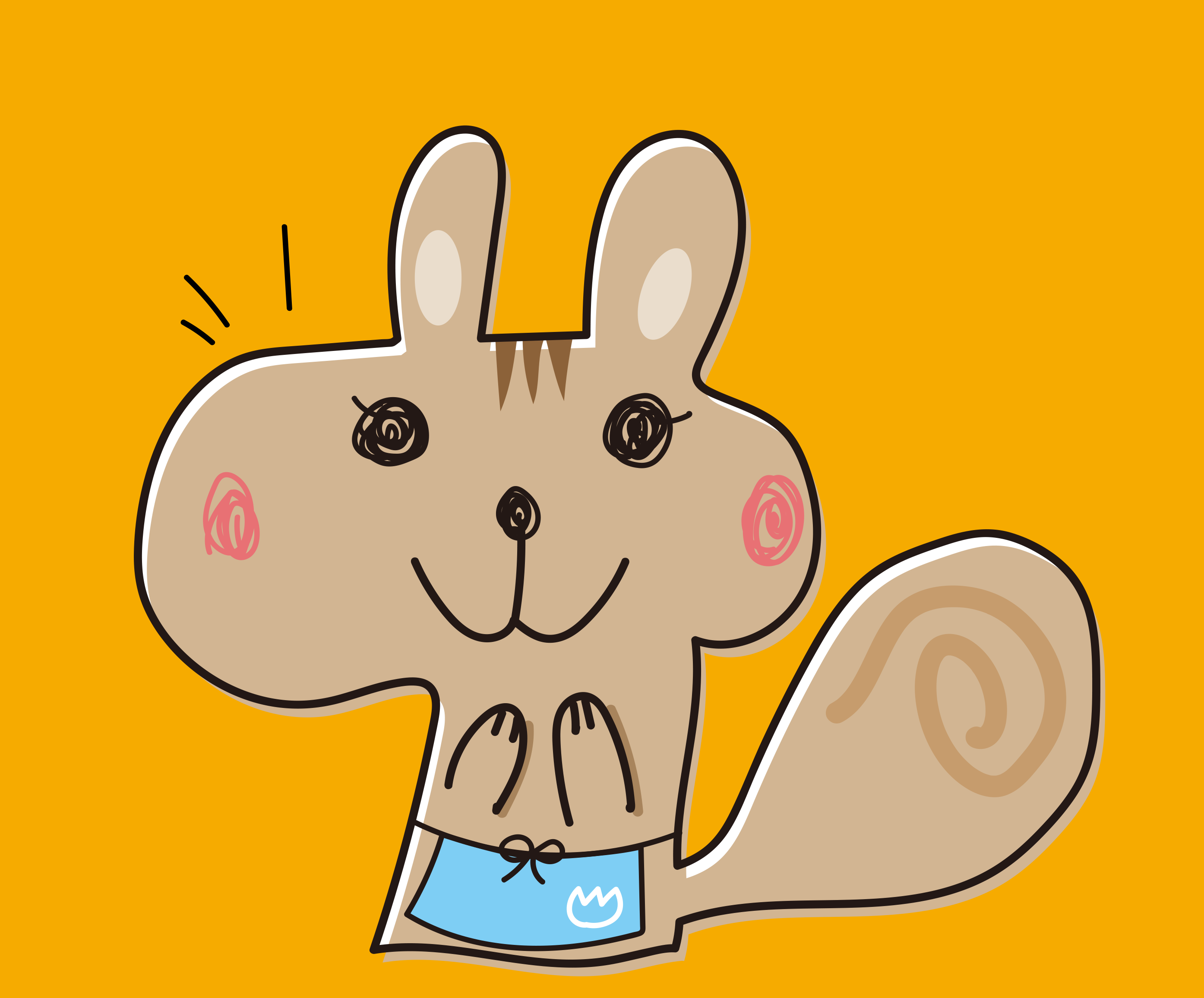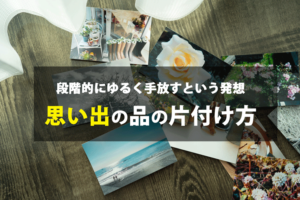モノは多いけど、工夫はすごいと感じています。

うちの実家は、ものが多いと感じます。
ですが、いたるところに工夫がされているので、「ものであふれている」という感覚はあまり感じません。
収納の工夫はいたるところにされています。
家族のせいにするまえに、じぶんのものを見直す
持たない暮らし・持ちすぎな暮らしなど、ミニマリスト的生活をしようと思っても、家族という名の壁がたちはだかります。
どんなに持たない暮らしをしようと思っても、家族がいると協力なしにはできない。
じぶんひとりが持たないようにがんばっても、家族がものを増やしていきます。
玄関の様子を写真に撮ってみてわかりました。
わたしの実家のものが多い原因は、わたしたち子どもにあるんだろうということです。
母の持ち物は事業用のものは別として、個人用のものは多くありません。
見渡してみても、本や裁縫道具くらいしかないのではないでしょうか。
その本も、ふせんがたくさん貼ってあり、かなり使い込んでいるのがみてとれます。
母にとっては30年以上前の本でも、なくてはならない大切な本。
ところが、じぶんが置いていった本をみると、たいした本はありません(苦笑)
漫画本ばかりです。
しかも、その漫画本のなかも、いまでも読んでしまうのはほんの数冊。
これは、持ち帰ることにします。
ほかは、処分します。
母が収納に工夫するようになったのは、わたしたち家族のためだったんだなとあらためて感じます。
母はものを増やさないように生活していた。
ここまでものを増やしてきたのは、わたしたち子ども。
でも、母だけが持たない暮らしをがんばっても、子どもたちは次から次にガラクタを買ってくる(母にとってはガラクタばかりだったでしょうね。笑)
実家が片付いていない原因は、じぶんたち子どもが作り出したのかもしれません。
母は、昔からストック品を持たないタイプです。
箱ティッシュやトイレットペーパーも、なくなってから買いにいく。
冷蔵庫のなかも、必要なものしか入っていません。
賞味期限が切れて捨てるなんてことはまったくないです。
わたしは、母のなにを見てきたのだろう。
こんなに循環ライフのお手本となるひとが身近にいたことに、いまごろ気づいてしまいました。
家族8人で暮らしてきたわりに、むかしはもっとすっきりしていた。
子どもが大きくなるに従って、ものが増えていった。
子どもたちは家を出ているはずなのに、ものは減っていない。
それは、わたしたち子どもが片付けていないから。
じぶんのモノはじぶんが責任もって、処分しよう。